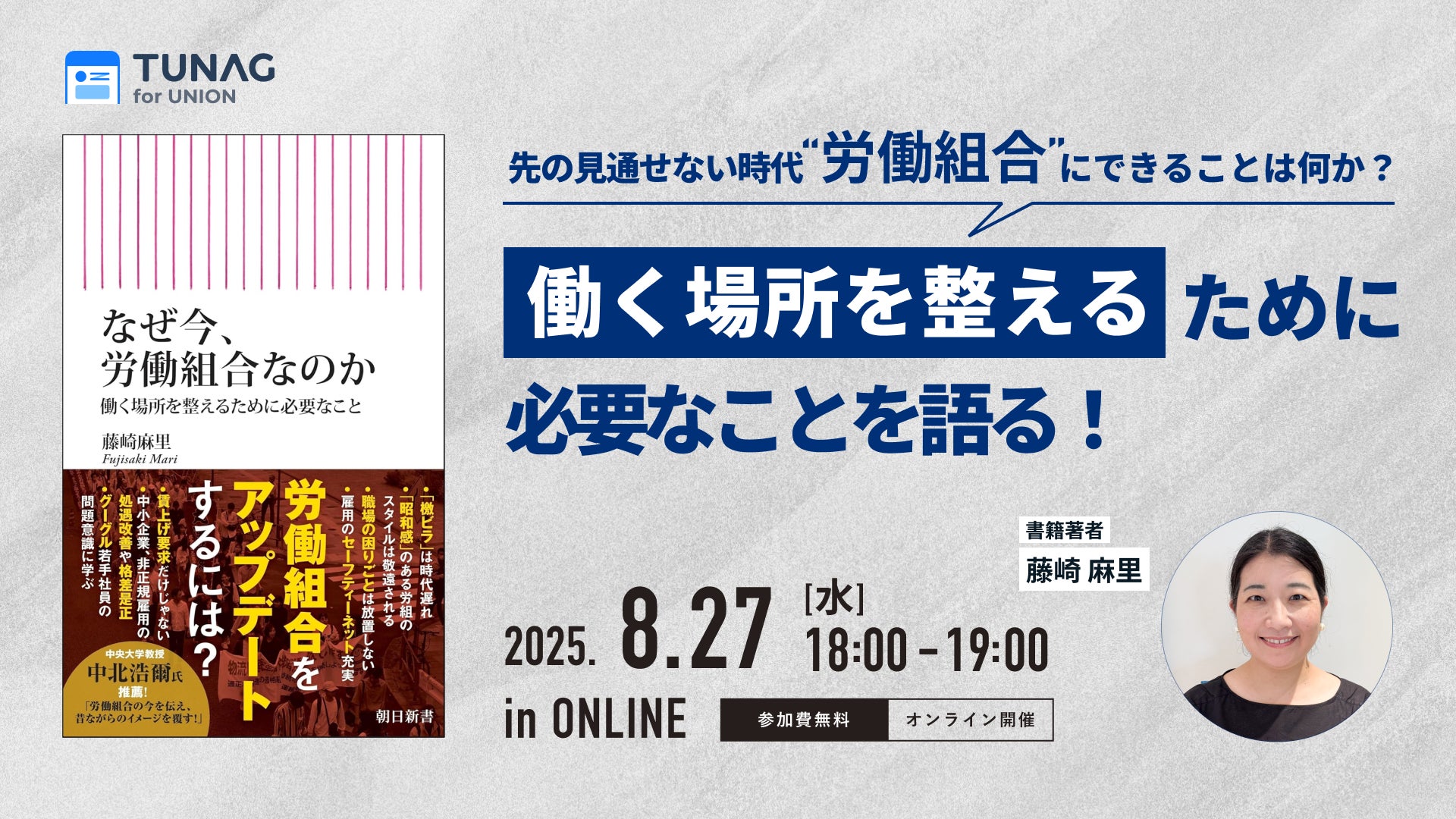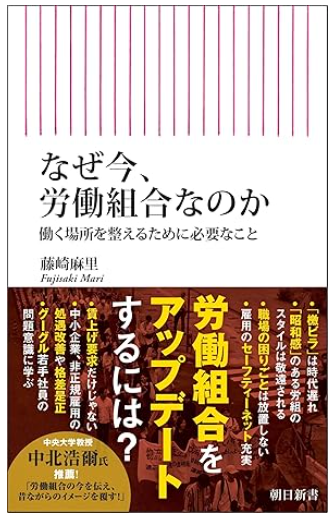働く場所を整えるために必要なこと
ひさしぶりの労働組合関連の書籍
「労働組合って会社とバチバチやるんでしょ!」
「ヘルメットやハチマキしてるんですか?」
いまだにこんな認識の人が結構います。労働組合だけが、昭和のイメージを払拭できていないように感じます。
今回はひさしぶりの労働組合書籍で、目次を見る限り硬派な内容が期待できそうです。さっそくamazonで購入して一気読みをしましたので、感想を共有させていただきます。
なぜ今、労働組合なのか
働く場所を整えるために必要なこと
著者 藤崎麻里(朝日新書)
2024年春闘の賃上げ率は5%台で33年ぶりの高水準となった。
だが、広がる格差や実質賃金に追いつかない賃上げなど課題は山積。
若い世代や非正規雇用など労働組合とつながらない人も多い。
一方、欧米では労組回帰の動きもある。
働く環境をよくするために今、労組に何ができるのか。
働き手、労働組合、政治のかかわりにも踏み込んだ意欲作!
現代における労働組合の役割や必要性
先の見通せない時代、労働組合にできることは何か。働き手を守るための社会的機能とは?2024年の春闘では賃上げ率が5%台と33年ぶりの高水準となった。「古い枠組み」と思われがちな労働組合だが、歴史的ベアに加え、「カスハラ対策」など新たな政策を生み出す力が注目されている。本来、経営者に対して弱い立場におかれる働き手が、対等な立場で賃金や働く場所のルールを議論できる仕組みが労働組合だ。だが、活動を知らない世代が増え、働き方が多様化する時代、労組とつながらない人たちは少なくない。格差拡大の今、産業の環境変化に対応できる人材育成の仕組みや、雇用のセーフティーネット構築など労組が取り組むべき課題は多い。
目次
1 日本編ー現場から(職場の働きやすさをつくるー「カスハラ」の舞台裏/フリーランス・雇用されない働き方ー成長産業や人手不足なのに賃金が上がらない/「職場をカスタマイズする方法」-メディアパーソナリティー小島慶子さんの場合/中小の春闘ー変化のうねりは鳥取から)/2 日本編ー政策提言(「官製春闘」の実態ー最大の賃上げ策は労組を増やすこと?/リスキリングースウェーデンの労使が作った枠組み/ワークルールー学校教育で広がらない「働く上での基本ルール」/外国人の相談窓口ーNPOと地方連合の連携/働く人の視点を政治に生かすためには/労働組合のこれから)/3 日本編ー労働組合の可能性(領域を広げるー組合員以外のために何ができるのか/労働組合を改革する/NPOとつながる意味/社会でも支えるという発想)/4 米国編ー現場から(サンダース委員会ー「企業の強欲とたたかう」/中間層をつくるために/ボトムアップからの改革は?-全米自動車労働組合(UAW)の変化/伝統的労組の変化ーシカゴ教職員組合の「歴史的」転換点/新しい「労組」の誕生ーグーグルで始まった社会運動)
著者 藤崎麻里(フジサキマリ)
1979年生まれ。朝日新聞記者。経済部、政治部などを経て、GLOBE編集部。経済部では経済産業省、エネルギー、金融、IT、総務省、連合など労働分野を担当した。一橋大学大学院社会学研究科ならでにロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)大学院国際関係学科で修士課程を修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
読後 変わる時代の、変わらぬ課題に挑む羅針盤
『なぜ今、労働組合なのか~働く場所を整えるために必要なこと』を読んで
2024年の春闘で33年ぶりの高い賃上げ率が実現し、労働組合の存在意義が再び注目されています。しかし、多くの組合役員が感じている通り、この歴史的なベアの裏側には、広がる格差、実質賃金が追いつかない現実、そして若い世代や非正規雇用の労働者との断絶といった、山積する課題があります。朝日新聞の記者が多角的な視点で取材した本書『なぜ今、労働組合なのか~働く場所を整えるために必要なこと』は、まさにそうした現代の労働組合が直面する課題の核心に迫り、未来への道筋を示唆してくれる一冊です。
過去の成功体験から抜け出し、新たな役割を模索する
本書は、労働組合が「単なる賃上げ交渉の担い手」という古い枠組みから脱却し、社会全体のセーフティーネットとして機能すべきだと強く訴えています。特に目を引くのは、アニメ制作業界のように人手不足でありながら賃金が上がらない構造的な問題や、フリーランス・非正規雇用といった「労働組合とつながらない人々」にどう手を差し伸べるかという問いです。これまでの組合活動では十分にカバーしきれなかった領域に踏み込み、社会の多様なアクター(NPOや政治)と連携することで、より包括的な労働環境の改善を目指すべきだという著者の提案は、現在の組合活動に行き詰まりを感じている執行部の皆様にとって、大きなヒントになるでしょう。
具体的な事例が示す、変化への希望
本書のもう一つの大きな魅力は、日本国内の中小企業の春闘事例から、アメリカのシカゴ教職員組合や全米自動車労働組合(UAW)の歴史的改革まで、具体的なケーススタディが豊富に紹介されている点です。特に「ボトムアップからの改革」としてUAWが示唆する、組合員一人ひとりの声を組織運営に反映させていく姿勢は、組合員の活動参加率低下に悩む多くの組合にとって、再生への突破口となり得ます。
また、カスハラ対策やリスキリング(学び直し)といった、現代の働き手が直面する具体的な課題に対し、労働組合がどのように関わっていくべきかという提言は、今後の活動計画を立てる上で非常に実践的です。
組合員と共に、未来の働き方を「再設計」する
本書は、決して「労働組合万歳」という一方的な礼賛の書ではありません。むしろ、これまでの活動に対する厳しい批判や、組合員が抱く不信感にも向き合っています。しかし、その上で、労働組合は「声の大きな一部多数を守る組織」ではなく、「働く人々の権利を守り、人間らしい労働環境を追求する」という本来の役割に立ち返ることの重要性を力強く語っています。
定年後の働き方や、キャリアの再設計が叫ばれる現代において、働く場所をより良くすることは、私たち自身の未来をより良くすることに他なりません。本書は、組合員が主体的に「自分たちの未来」を考えるきっかけを与えてくれるはずです。
この書籍は、労働組合の未来を真剣に考える執行部の皆様にとって、一読する価値のある内容です。過去の延長線上にない、新しい時代の組合活動を構想する上で、きっと羅針盤となるでしょう。
また、本書を読書研修のテーマとして活用することも有効です。組合役員同士で本書の内容について議論を深めることで、新たな気づきやアイデアが生まれ、組織としての結束力が高まることが期待できます。今こそ、組合員と共に「なぜ今、労働組合なのか」を問い直し、これからの活動に活かしていきましょう。
藤崎麻里 講演会