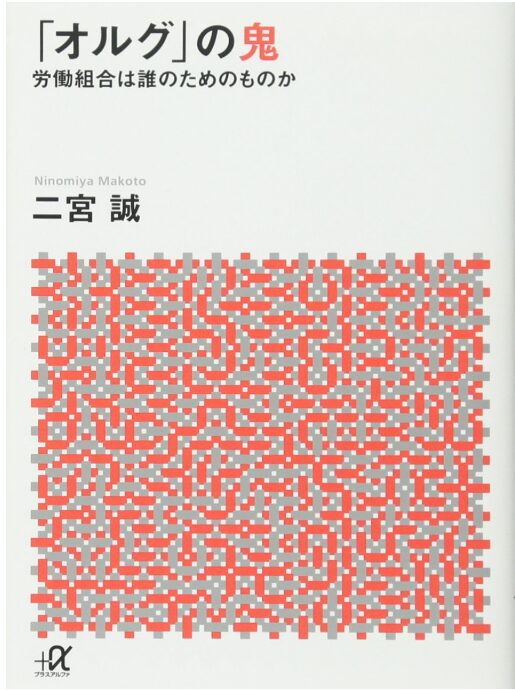知識だけでは人は動かせない。そこに「情熱」はあるか。
昭和の労働組合から何を学ぶのか…
別記事で「なぜ今、労働組合なのか~働く場所を整えるために必要なこと」(朝日新書)著者 藤崎麻里
を紹介しましたが、未来を議論するうえでは過去を振り返ることも重要です。
この記事でご紹介するのは、実際の現場で戦ってきた記録です。時代や立場が異なりますが、それぞれの視点で読み解いてください。
格差に苦しむ、すべての労働者のために、時に怒り、時に涙した活動の記録、
労働運動ひとすじ40年。全国各地で労働組合の組織化を指揮してきた「伝説のオルガナイザー」が、すべてを語った。ケンカ同然のストライキ、倒産企業の整理でヤクザと対立、労組結成を嫌がる社長への直談判――。格差に苦しむ、すべての労働者のために、時に怒り、時に涙した活動の記録。
労働運動ひとすじ40年。全国各地で労働組合の組織化を指揮してきた「伝説のオルガナイザー」が、すべてを語った。ケンカ同然のストライキ、倒産企業の整理でヤクザと対立、労組結成を嫌がる社長への直談判――。
格差に苦しむ、すべての労働者のために、
時に怒り、時に涙した活動の記録。
現場の熱と、人を動かす情熱が詰まった一冊
『「オルグ」の鬼 労働組合は誰のためのものか』を読んで
『「オルグ」の鬼』という強烈なタイトルが示す通り、本書は、労働運動一筋40年、「オルグ」と呼ばれる組織化の最前線で闘い続けてきた二宮誠氏の半生と哲学が詰まった熱量あふれるドキュメントです。2024年の春闘で歴史的な賃上げが実現する一方、労働組合の組織率は年々低下し、その存在意義が問われる現代において、本書は「なぜ今、労働組合が必要なのか」を改めて問い直す貴重な示唆に満ちています。
知識だけでは人は動かせない。そこに「情熱」はあるか。
著者の二宮氏は、ときにヤクザと対峙し、ときに経営者と膝を突き合わせて交渉を重ねてきました。その活動記録は、教科書的な労働法や組合運営論では決して語られない、泥臭くも人間味あふれるエピソードの連続です。
彼が説く「組織化は、情報と情熱」という言葉は、現代の組合活動にも通じる本質的なメッセージだと感じました。執行部の多くが多忙な業務の合間に組合活動に従事している現実がある一方で、組合員との対話がおざなりになり、活動が形骸化している組合も少なくありません。本書を読むと、組合員一人ひとりの「困りごと」に徹底的に寄り添い、その声なき声を聞き出すことが、いかに組織化の第一歩であるかを痛感させられます。
また、倒産企業の整理やストライキなど、壮絶な修羅場をくぐり抜けてきた著者の経験は、現在の労使関係が希薄化し、メンタルヘルスやハラスメントといった新たな問題が浮上している状況において、組合役員が持つべき「人の心に寄り添うプロの仕事」とは何かを教えてくれます。
組合活動を「誰のため」に行うのか
本書の核心にあるのは、「労働組合は誰のためのものか」という問いです。著者は、格差に苦しみ、声を上げられないすべての労働者のために、ときに怒り、ときに涙しながら活動を続けてきました。これは、組合員である正社員だけでなく、非正規雇用や派遣社員、そして組合に加入していない労働者の声にも耳を傾けるべきだという、現代の労働組合が担うべき使命を改めて私たちに投げかけています。
特に、ゲスト対談で登場する株式会社エコスやダイナムジャパンホールディングス、ニトリホールディングスといった著名企業の経営者との対話は、労使が対立するだけでなく、互いの立場を理解し、協調していくことの重要性を示しています。組合活動は、単なる闘争ではなく、働く環境をより良くするために経営側と建設的な対話を築くための手段なのだと、改めて認識させられました。
執行部の皆様へ:未来の組合活動を構想するための羅針盤として
本書は、単なる昔話の記録ではありません。
労働運動の「本質」と「情熱」を学ぶための、現代の組合役員にとっての必読書です。
執行部の皆様は、ぜひ一度手に取ってみる価値があります。
また、この書籍を読書研修に活用することで、執行部メンバーが自身の活動の原点を見つめ直し、現代の組合員に「どう響くか」を議論する良い機会になるでしょう。「情報と情熱」を再認識し、組合員一人ひとりの心に火を灯すような活動を再構築するためのヒントが、この一冊には詰まっています。
現場の熱と、人を動かす情熱が詰まった一冊
『「オルグ」の鬼 労働組合は誰のためのものか』を読んで
『「オルグ」の鬼』という強烈なタイトルが示す通り、本書は、労働運動一筋40年、「オルグ」と呼ばれる組織化の最前線で闘い続けてきた二宮誠氏の半生と哲学が詰まった熱量あふれるドキュメントです。2024年の春闘で歴史的な賃上げが実現する一方、労働組合の組織率は年々低下し、その存在意義が問われる現代において、本書は**「なぜ今、労働組合が必要なのか」**を改めて問い直す貴重な示唆に満ちています。
知識だけでは人は動かせない。そこに「情熱」はあるか。
著者の二宮氏は、ときにヤクザと対峙し、ときに経営者と膝を突き合わせて交渉を重ねてきました。その活動記録は、教科書的な労働法や組合運営論では決して語られない、泥臭くも人間味あふれるエピソードの連続です。
彼が説く「組織化は、情報と情熱」という言葉は、現代の組合活動にも通じる本質的なメッセージだと感じました。執行部の多くが多忙な業務の合間に組合活動に従事している現実がある一方で、組合員との対話がおざなりになり、活動が形骸化している組合も少なくありません。本書を読むと、組合員一人ひとりの「困りごと」に徹底的に寄り添い、その声なき声を聞き出すことが、いかに組織化の第一歩であるかを痛感させられます。
また、倒産企業の整理やストライキなど、壮絶な修羅場をくぐり抜けてきた著者の経験は、現在の労使関係が希薄化し、メンタルヘルスやハラスメントといった新たな問題が浮上している状況において、組合役員が持つべき「人の心に寄り添うプロの仕事」とは何かを教えてくれます。
組合活動を「誰のため」に行うのか
本書の核心にあるのは、「労働組合は誰のためのものか」という問いです。著者は、格差に苦しみ、声を上げられないすべての労働者のために、ときに怒り、ときに涙しながら活動を続けてきました。これは、組合員である正社員だけでなく、非正規雇用や派遣社員、そして組合に加入していない労働者の声にも耳を傾けるべきだという、現代の労働組合が担うべき使命を改めて私たちに投げかけています。
特に、ゲスト対談で登場する株式会社エコスやダイナムジャパンホールディングス、ニトリホールディングスといった著名企業の経営者との対話は、労使が対立するだけでなく、互いの立場を理解し、協調していくことの重要性を示しています。組合活動は、単なる闘争ではなく、働く環境をより良くするために経営側と建設的な対話を築くための手段なのだと、改めて認識させられました。
執行部の皆様へ:未来の組合活動を構想するための羅針盤として
本書は、単なる昔話の記録ではありません。労働運動の「本質」と「情熱」を学ぶための、現代の組合役員にとっての必読書です。
執行部の皆様は、ぜひ一度手に取ってみる価値があります。
また、この書籍を読書研修に活用することで、執行部メンバーが自身の活動の原点を見つめ直し、現代の組合員に「どう響くか」を議論する良い機会になるでしょう。「情報と情熱」を再認識し、組合員一人ひとりの心に火を灯すような活動を再構築するためのヒントが、この一冊には詰まっています。
プロ講師ドットコムは、顧客の課題を伺い、適切な講師、研修企画を提案することを事業しています。しかくかならずしも外部講師を招聘しなくてはいけないことはありません。学ぼうと思えば、予算がなくてもいくらでもオプションがあります。
例えば、本記事でもご提案しております「読書研修」は、参加者が同じ本を事前に読んできて、それぞれの感じたことを共有します。人によって刺さる部分がこんなに違うのかと驚かれるでしょう。
この時、大切なことは他人の意見を否定しないこと。
「A」という感想をもった人を「Bに決まっている」なと言ってはいけません。
「A」の意見も、「B」も「C」もそれぞれいいのです。
ディスカッションを通じて、それぞれが「A´」「B´」「C´」になれば、それが成果です。
本1冊が難しければ、何らかの本もひとつの章でもいいのです。
意外に楽しいですよ。是非、試してください。